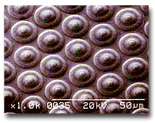�d��
�d��
�@�d���ielectroforming�j�͓d�C�߂����𗘗p���ĕi���i���^�i�j����邱�Ƃ��疽�����ꂽ���t�ł���B
�����ŁA�߂����͕\�ʏ����Z�p�A�d���͐��^���H�Z�p�ƕ��ނ��邱�Ƃ��ł���B
�d���@�ł́A�܂���^�i���^��}�X�^�[�A�}���h�����Ƃ��Ă��j�ɓd�C�߂����A�܂��͖��d���߂����@�ɂ�������͏o��������A���̋������^���甍�����Đ��i�Ƃ���B
��^�������̏ꍇ�ɂ͔����̂��߂̕\�ʏ������{���A������̏ꍇ�ɂ͂߂������s�����߂̓��d���������{���K�v������B
�@���̋Z�p�̓����͕�^�̐����ȓ]�ʐ��ɂ���A�Â��������ł�R�[�h�̌��ł̍쐻�Ɏg���Ă����B�d���͕�^�̌`��𒉎��ɐ��m�ɕ��ʂ����̂ŁA��^�̐��x������������قǁA���ꂩ��쐻�����d�����i�̐��x�������Ȃ�B
�]���āA����̂悤�ȃT�u�~�N�����̉��H���x���v�������n�C�e�N�Љ�ł́A���̋Z�p���Ăыr���𗁂тĂ���B���Ȃ킿�A�]���̋@�B���H�Z�p�ł͍쐻�ł��Ȃ��悤�Ȓ����ו��i�̐��삪�t�H�g���W�X�g�@�̋Z�p�p���ĉ\�ƂȂ�A�܂��A�@���[�U�[�f�X�N�̂悤�Ȑ����ő�ʐ��Y���K�v�Ȃ��̂̐��^�p���^�̐����Ȃǂɂ����͂����Ă���B
a�j�d�����H�̓���
�@�d�����H�̓����͂��̗D�ꂽ�]�ʐ��x�ɂ��邪�A���̐��x�͒��^�̕\�ʂ�0.1��m�@�̉��ʂ�]�ʂł��A���@���x�ł͉~���`���10��m�ȓ��A���ʌ`��ł�1m�ɂ���20��m�ȓ��ɃR���g���[�����\�ł���Ƃ���Ă���B�܂��A���H�������画��悤�ɁA�������H���\�Ȃ��ƂƁA��^�̍ޗ��ɂ͂��̖ړI�ɂ��A�������������킸���L���ޗ����g�p�ł��邱�Ƃł���B
b�j�d���p�߂�������
�@�d���p�̂߂��������Ƃ��ẮA������уj�b�P������ʓI�ł���A�����i�̍쐻�ɂ͋���₪�g���Ă����B
�������A�ߔN�̂߂����Z�p�̐i���ɔ����A��萫�\�ɗD�ꂽNi-Co�������͂��߁A�e�핡�����U�߂����Ȃǂ��g����悤�ɂȂ����B
�@�d�����H�ɂ����čł��d�v�Ȃ��Ƃ́A�������͂̏o���邾���������߂������g�����Ƃł���B
��ʂɁA�߂����w�ɂ͑傫�ȓ������͂����݂��邽�߁A����œd�����s���ƁA���i�ɘc�������A�ό`����̂Ő��x���������ቺ����B�]���āA�������͂̔������Ȃ��悤�Ȃ߂������g����߂���������I�肷��K�v������B�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�j�b�P���߂����ł̓X���t�@�~���_����������͌������Ƃ��ẴT�b�J���������L�����p����Ă���B
c�j�@��^�̍ޗ��Ƃ��̕\�ʏ���
�@��^�Ɏg����ޗ��́A�����ł͓S�A�X�e�����X�A������ѓ������A�A���~����уA���~�����A�����A����������A������ł̓G�|�L�V�����A�����A�e��v���X�`�b�N�A�p�A�K���X�A�S���A�Z���~�b�N�A��v��������B
�����̍ޗ��͂��̖ړI�ɂ��g���������Ă��邪�A�����̏ꍇ�ɂ͂߂�����̔�����e�Ղɂ��邽�߂��̕\�ʂɔ����w���`�������A������̏ꍇ�ɂ͓`������t�^���邽�ߓd�����疌��݂���K�v������B
�����w�ɂ͂��ꂼ��̋����̎_�����≻�����疌���p�����A�`�����̕t�^�ɂ͋⋾�����@�△�d���߂����@�A��������������̓h�z�@�����p������B
d�j�@�d���̉��p��
| �������^�F |
|
�ʏ�̋��^�͋@�B���H����d���H�Ŏ�ɍ���Ă���B�����d���@�ō��Ǝ��̂悤�ȗ��_������B���ɐ��x���������ƁA���ɋ��^����������ł��邱�Ƃɂ���B���p��Ƃ��Ă̓v���X�`�b�N�̎ˏo���^�p���^��_�C�J�X�g�p���^�A�K���X�@�ۋ������������p���^�Ȃǂ�����B
|
| �������̐����F |
|
�v�����g��łɗp�����Ă��铺���͂�������]���Ă���h�����̈ꕔ���߂����t�ɒЂ��Ă߂������s���A�����A���I�ɔ������Đ�������Ă���B�����悤�Ȑ��@�ɂ��j�b�P����S�̔��Ȃǂ��쐻�����B
|
| ���������b�V���A�t�B���^�[���F |
|
��^��Ɍ��������̃t�H�g���W�X�g�@�Ń��b�V����t�B���^�[�̐}�`���p�^�[�j���O�����≏�疌��݂�����A�߂������s����������Đ��i�Ƃ���B�g�߂ȂƂ���ł͓d�C�J�~�\���̐n�����̕��@�ō���Ă���B
|
| �����A�L���،��p����ŁF |
|
�ɂ߂Đ����Ȉ�����s���Ƃ��ɂ́A�d���@�ɂ�����ł��쐻����B�Ⴆ�A��������p�̌��ł͗D�ꂽ�����t�ɂ��ɂ߂Đ��I�Ȃ��̂��쐻����A������^�Ƃ��Ď��ۂ̈���ł�������������B
|
| ���ǂݏo���f�X�N�F |
|
���̃f�X�N�͉f���Ɖ��̍Đ��ɗp�����Ă���B�����̃f�[�^�͒ʏ�A�[��0.1��m�A��0.4-0.6��m�A��́@0.5-2��m�̐r�b�g��������ɕ��g���b�N�Ƃ��ċL�^����Ă���B�g���b�N��1.6��m�Ԋu�Ƃ����1���̃f�X�N�ł͑S��30km�ƂȂ�A���̏��ʂ͖�3�~1010���r�b�g�A�f�����Ԃɂ��Ė�30���ƂȂ�B���̂悤�Ȃ��̂�d�����H����ɂ͓��ʂɐ���������N���[�����[���ł̍�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
|
| ����i�̍쐻�F |
|
��ʂ̌i�����ɂ�鑕���i�̍쐻�̓��X�g���b�N�X�@��v���X�@�ō���邪�A�d���@���g���ƌy�ʂŕ��G�Ȍ`��̕����ʐ��Y�ł��闘�_������A�ߔN���̎�@�ɂ�鐻���@�����ڂ���Ă���B
|
| �q��F���W�F |
|
�y�ʂŐ����ȓ��g�ǂ�A���e�i���͂��߁A�X�y�[�X�V���g����G�C���A�����P�b�g�̃G���W���̎�v���i���d���@�ō쐻����Ă���B |
�@�ȏ�A�d���@�̉��p����������q�ׂ����A�����͎��p������Ă�����̂̈ꕔ�ɉ߂����A�����Ԃ�Ɠd�A�Y�Ƌ@�B�Ȃǂ̕���ł͍X�ɑ����̕��i�����̕��@�ō쐻����Ă���B
����̓}�C�N���}�V���̕��i�쐻�Ƃ��A�z���O���t�B�Ȃǂ̌��w�֘A����A�G���N�g���j�N�X�ȂǁA��X�̐�[�Z�p����ł̊��p�����҂����B
�@ |